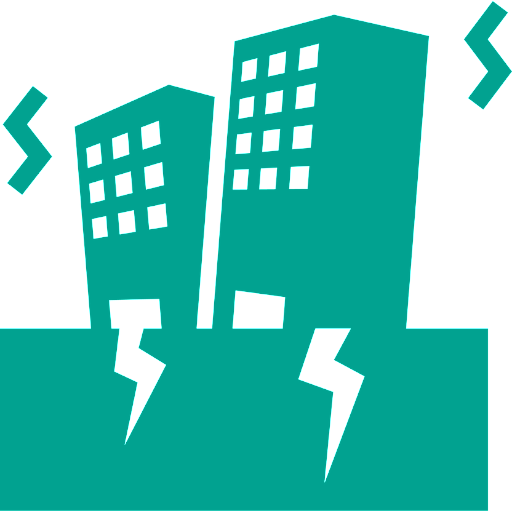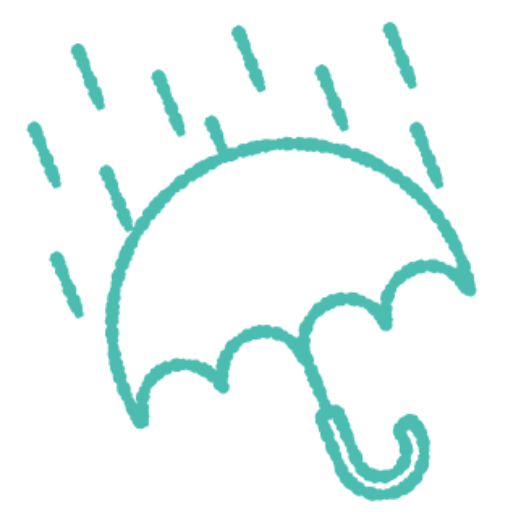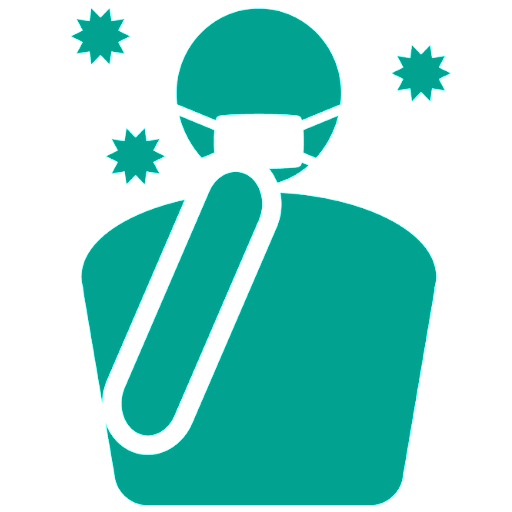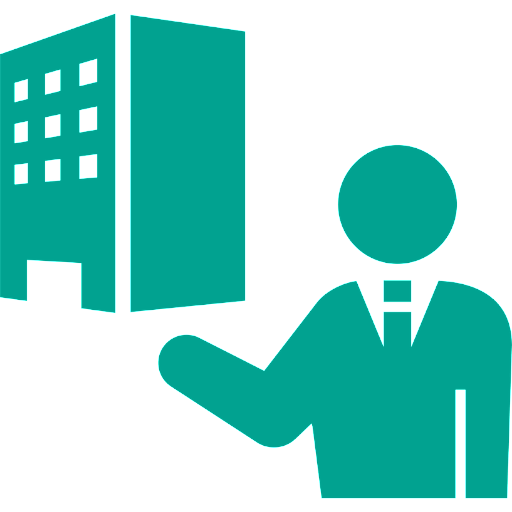新潟中越地震
概略
発生日時
2004年10月23日 午後5時56分
震央
新潟県中越地方
震源
北緯37度17.5分、東経138度52分、深さ13km
規模
マグニチュード6.8
最大震度
震度7(川口町)
被害
- 死者68名
- 負傷者4,795名
- 全壊家屋3,175棟
- 避難者数はピーク時に約10万人
経済被害
約3兆円
特徴
広範囲な被害
新潟県中越地方を中心に大規模な地震が発生し、山間部を含む広範囲で地滑りや住宅倒壊が相次いだ。
震度7の揺れ
最大震度7を観測し、強い余震が長期間続いたことで被害が拡大した。
インフラの寸断
電力や水道、道路が寸断され、孤立地域が多発したため、支援活動が困難を極めた。
避難生活の長期化
冬季を迎える時期に発生したため、寒冷な環境での避難生活が長期化し、被災者に大きな負担を与えた。
課題
1.山間部の被害
山間部を震源とする地震であり、家屋やインフラの被害が甚大でした。
2.土砂災害
地震による地盤の緩みにより、多数の土砂災害が発生しました。
3.ライフラインの寸断
電力、ガス、水道などのライフラインが広範囲で寸断されました。
4.孤立地域への支援
道路の寸断により孤立した地域への支援が遅れました。
5.情報伝達の混乱
地震発生直後、情報伝達に混乱が生じました。
事例
自衛隊の活躍
ボランティア活動の活発化
国際社会からの支援
諸外国からの救援が被災地復興に大きく貢献した。
対策
耐震性の高い建築物の普及
建築物の耐震基準を見直し、耐震性の高い建物の普及を促進する。
土砂災害対策の強化
地盤の調査を徹底し、土砂災害の危険性が高い地域での対策を強化する。
ライフラインの復旧体制の強化
災害時に迅速にライフラインを復旧できる体制を整備する。
孤立地域への支援
代替交通手段の整備、孤立集落の特性を踏まえた防災計画を策定する。