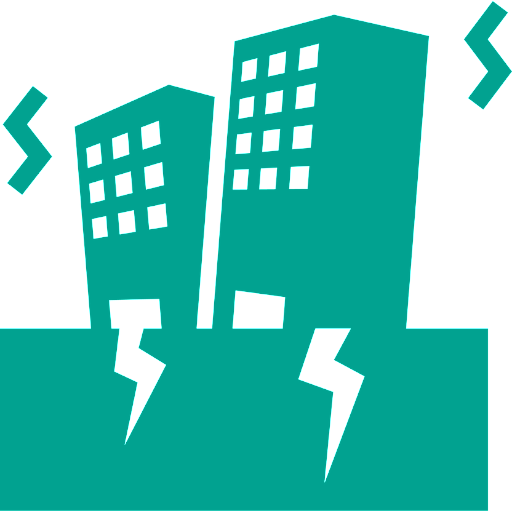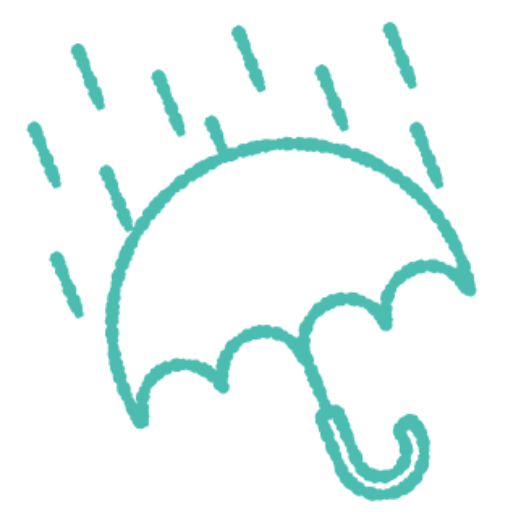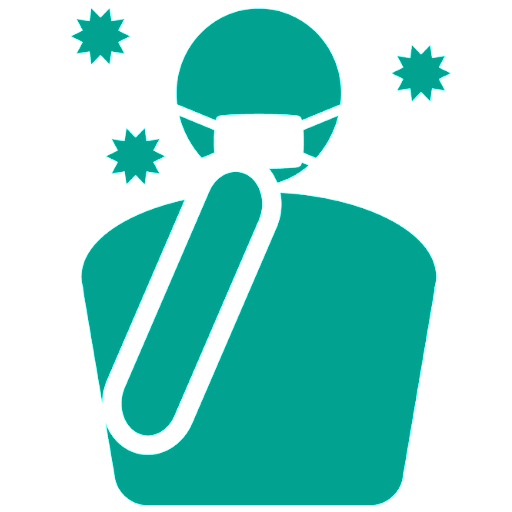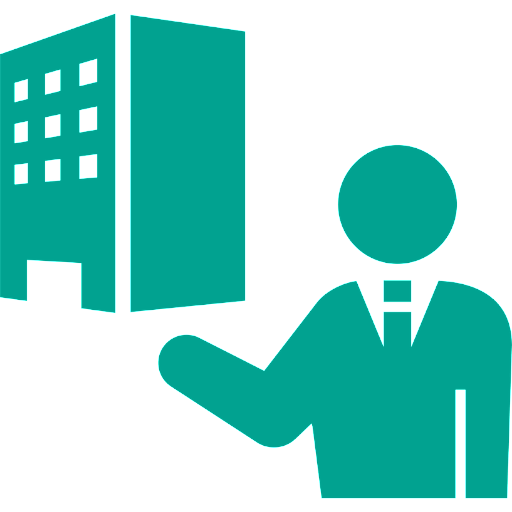熊本地震
概略
前震
2016年4月14日午後9時26分、マグニチュード6.5の地震が発生
本震
2016年4月16日午前1時25分、マグニチュード7.3の大地震が発生
最大震度
震度7(熊本県阿蘇市、南阿蘇村、西原村、産山村など)
被害
- 死者298名
- 行方不明者2名
- 重軽傷者2万4,731名
- 全壊8,667棟
- 半壊3万4,719棟
経済被害
約4.6兆円
特徴
2度の震度7の地震
前震(4月14日)と本震(4月16日)の2回にわたり震度7を観測し、大規模な被害をもたらした。
甚大な住宅被害
多くの住宅が全壊または半壊し、避難生活を余儀なくされた被災者が多数発生した。
インフラ被害と交通の麻痺
電力や水道などのライフラインが寸断され、阿蘇大橋の崩壊など交通インフラにも深刻な被害が及んだ。
山間部での孤立地域の発生
山間部で孤立した地域が多く発生し、支援物資の輸送や被災者の救助が困難を極めた。
課題
1.山間部の被害
地震により山間部の家屋やインフラが甚大な被害を受けました。
2.土砂災害
地震による地盤の緩みにより、多数の土砂災害が発生しました。
3.ライフラインの寸断
電力、ガス、水道などのライフラインが寸断され、特に水道の復旧には約3ヶ月を要した地域もありました。
4.孤立地域への支援
道路の寸断により孤立した地域への支援が遅れました。
5.情報伝達の混乱
地震発生直後、情報伝達に混乱が生じました。
事例
自衛隊の活躍
ボランティア活動の活発化
国際社会からの支援
諸外国からの救援が被災地復興に大きく貢献した。
対策
耐震性の高い建築物の普及
建築物の耐震基準を見直し、耐震性の高い建物の普及を促進する。
土砂災害対策の強化
地滑りや崖崩れを防ぐための防災工事や監視体制を整備。
ライフラインの復旧体制の強化
地震後の電気、ガス、水道などの早期復旧を目指した体制づくり。
孤立した地域への支援体制の強化
山間部や離島など孤立しやすい地域への緊急支援体制を強化。
情報伝達の強化
多言語対応や迅速な情報提供体制を構築し、避難行動を円滑化。