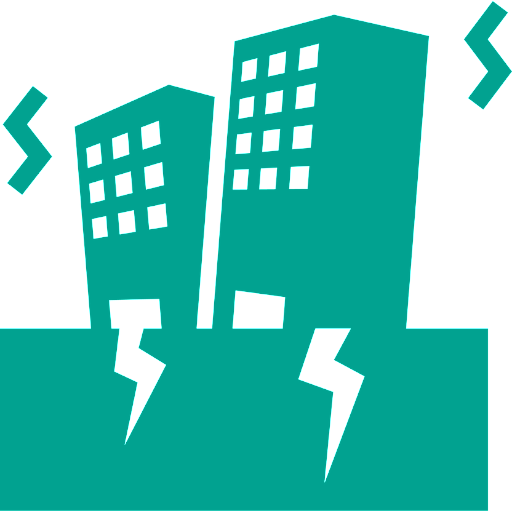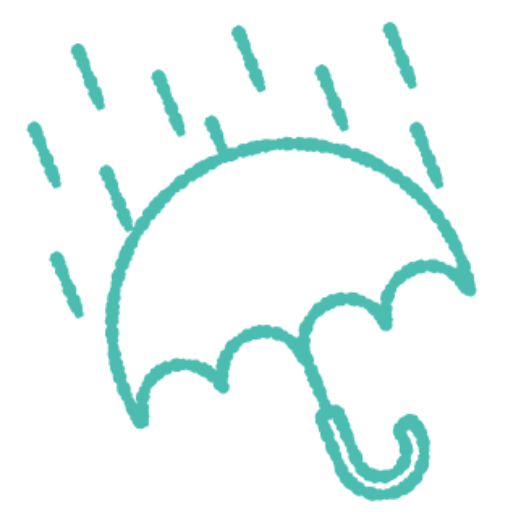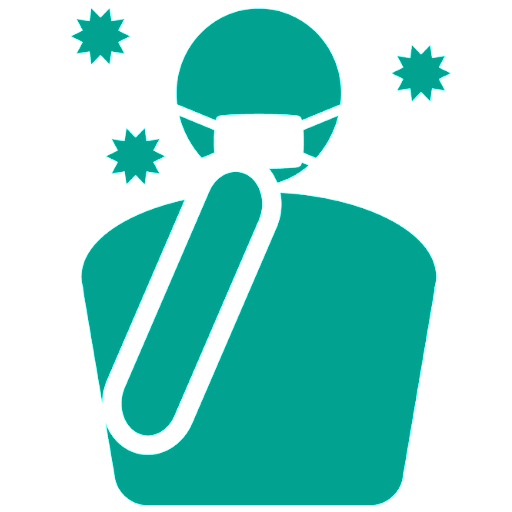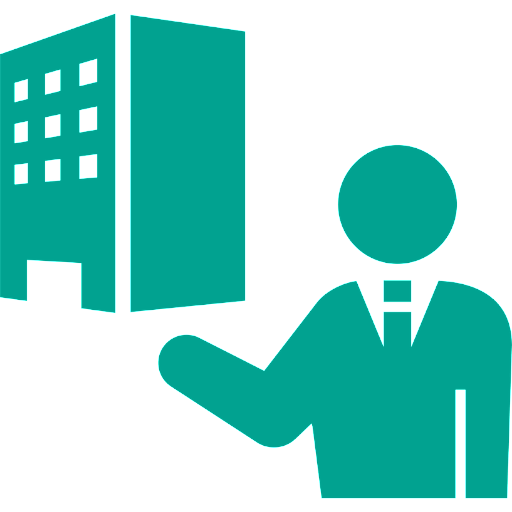阪神・淡路大震災
概略
発生日時
1995年1月17日午前5時46分
震央
兵庫県南部
震源
淡路島北部震源: 北緯34度36分、東経135度02分、深さ16㎞
規模
マグニチュード7.3
最大震度
震度7(神戸市、芦屋市、宝塚市など)
被害
死者6,437名、重軽傷者43,792名、全壊10万4,906棟、半壊14万4,272棟
経済被害
約9.6兆円
特徴
・都市型地震
人口密集地で発生したため、住宅やインフラへの被害が甚大となり、火災や建物の倒壊が相次いだ。
木造建築物の脆弱性
多くの木造住宅が耐震性に欠けており、大規模な倒壊が発生した。
被害規模の大きさ
死者6,437名、経済損失約9.6兆円という大規模な被害を記録し、日本国内で大きな衝撃を与えた。
ボランティア元年
災害後に多くの市民がボランティア活動に参加し、日本の災害支援活動における転換点となった。
課題
1.都市型地震の被害の甚大さ
人口密集地を震源とする都市型地震のため、家屋やインフラへの被害が非常に大きかった。
2.木造建築物の多さ
当時の日本の住宅は木造が多く、地震に脆弱であった。
3.防災体制の不備
大規模地震への対応体制が十分ではなかった。
4.高齢者や障がい者の避難
高齢者や障がい者にとって、避難が困難な状況が発生した。
5.外国人の情報取得
外国人には日本語の情報が伝わりにくく、避難行動をとるのが難しかった。
6.被災者への支援
被災者への支援が不足し、早期の支援が求められた。
事例
ボランティア活動の活発化
NPO法人の活躍、民間企業の貢献
国際社会からの支援
諸外国からの救援が被災地復興に大きく貢献した。
対策
耐震性の高い建築物の普及
建物の耐震基準を強化し、耐震性の高い建築物を普及させる対策が必要。
防災体制の強化
地震発生時に迅速に対応できるよう、自治体や企業の防災体制を強化。
高齢者や障がい者への配慮
避難所のバリアフリー化や支援体制を整える。
外国人の情報提供
外国人にも理解できるよう、多言語での情報提供を強化する。
被災者への支援体制の強化
支援物資や避難所の整備を早急に行い、被災者への支援体制を強化。